岡崎市教育委員会 教育長 殿 2011年1月17日
岡崎市教育委員会 学校指導課
各学校 学校長 殿
教 頭 殿
教職員の在校時間等の状況記録及び勤務の改善についての申し入れ
岡崎市では、昨年9月から、県が作成した「在校時間等の状況記録」(Exelファイル)を使って、毎月の時間外・休日労働時間を記録するようになりました。平成22年3月5日に愛知県教育委員会教育長名で出された「勤務時間の適正な管理及び長時間労働による健康障害防止について」の通知の中で「教職員の勤務時間を適正に管理し、一人一人が健康な心身の状態の中で、学校教育に取り組めるように、また、仕事と子育て等の家庭生活の両立が図れるよう」にするためと、実施の趣旨が述べられています。
各学校では、管理職が教員の勤務実態を正確に把握し、長時間労働の実態がある場合は、産業医の面接を受けるなどの健康への配慮や勤務の改善措置をとることが、管理職や市教委に義務づけられています。
岡崎の学校では、これにもとづいて改善を試みる学校もある一方で、趣旨に全く反して、勤務の実態を隠す動きがあり問題です。そこで、記録の取り方及び勤務の改善について以下の申し入れをするものです。
記
1.趣旨に反する記録の取り方は直ちに止めること
①「100時間を超えたら、管理職から100時間以内に書き換えるよう言われた」とか「100時間を超えても、管理職から言われて書き直すのが面倒だから、100時間以内になるよう自粛している」という実態が、一部の学校であります。
②「教育論文を書くように言われて遅くまでやったが、自己研修扱いにして、勤務時間に入れるなと言われた」という事例もあります。これは、教頭が職員に話した後に校長が撤回した学校、職員が申し入れて撤回した学校もあります。
③土日の部活動で、手当をもらっている場合は、時間外労働に入れないようにする動きがあるとも聞きます。これは、時間外・休日労働時間の算出の仕方を故意に曲げようとしているか、無知をさらけだしているかです。手当の有無にかかわらず時間外・休日労働はカウントするのが当たり前です。
①~③の事例は、どれも長時間労働の実態を隠すための動きで、到底認められるものではありません。市教委は、各学校の実態を調査して、勤務時間の適正な管理に反する行為を直ちに止めさせるよう求めます。公文書で3年間保存となる記録簿に虚偽の記録を強要することは、違法な行為と言わざるを得ません。該当校は直ちに正常な記録ができるように是正するよう求めます。
100時間超の職員が多数いる実態を、虚偽の申告で隠す行為は、勤務の改善を目的とした趣旨から大きく逸脱していることを、自覚していただきたいと思います。
2.80時間・100時間超の職員は医師による面接指導を
時間外・休日労働時間が80時間、100時間を超えると、表のように労災認定の数が急激に増えます。この事実から、労働安全衛生法では、80時間
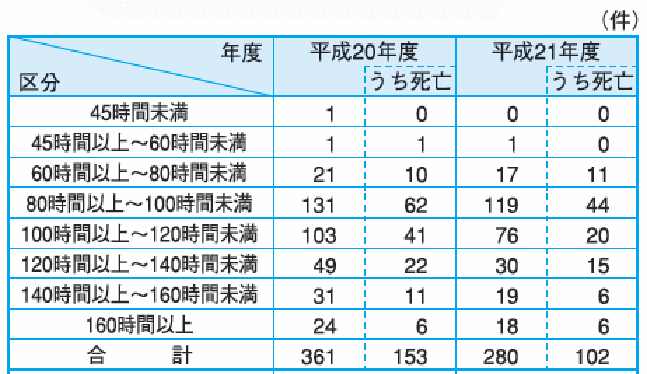 ・100時間を超える場合、労働者が産業医の面接を受けることができるようにしなければならないと、事業者(管理職・市教委)に義務づけています。岡崎の学校から過労死の先生を出さないために、管理者の義務を果たすよう求めるものです。
・100時間を超える場合、労働者が産業医の面接を受けることができるようにしなければならないと、事業者(管理職・市教委)に義務づけています。岡崎の学校から過労死の先生を出さないために、管理者の義務を果たすよう求めるものです。3.長時間労働をなくし教職員の命と健康を 守るために、今すぐできる勤務の改善を
同時に、長時間勤務が連続することのないように、事業者は事後措置(改善策)を講じなければなりません。
①時間外勤務をなくすために、当面以下の業務の割り振り変更(回復措置)を管理職の責任で行うことです。
① 職員会議(学年会・公務分掌上の会義)、職員 研修、研究授業の準備
② 学校行事(準備時間をふくむ)(例)運動会のための早朝練習・準備もふくむ (厚生労働省 資料)
③ 児童・生徒の指導にかかわる業務
④ PTA活動、地域教育会議の活動
⑤ 家庭訪問・保護者面談・評価活動・成績処理・通知票や指導要録等の記入時間
⑥ その他翌日以降に持ち越すことのできない重要な校務
⑦ 翌日以降に持ち越すことの出来ない授業資料の作成
例:日直、職員会議、現職教育、成績処理などで時間外勤務となった分を、割り振り変更で、長期休業中に13時間とるようにした学校。
②職員会議や授業研究会、現職教育があるときは、下校時刻を早めて時間内に会議を終える
(清掃時間、英語・学習タイムをなくす、短縮などの措置で)
例:昼から子どもを帰して、部活もやめて、職員会議を昼間に行った(中学校)
③部活動の時間を見直す・・・終了時刻を早める、朝練の時間を短縮、部活のない日を設定など
例:校長から勤務時間縮減の案が出され、超過勤務の大きな要因は部活動であるとし、夏の部活 終了を15分短縮。土日の部活は両日で8時間までとする。(中学校)
例:11・12月の部活は以前からなしに(小学校)
④主事訪問、指導員訪問で作成する指導案について、必要以上に点検・指導しない
⑤教育論文を強制しない
⑥学校や教科部会で年度末に作成する実践記録などをやめる
⑦月1回、ノー残業DAYを設けて、全員早く帰る
⑧その他に
例:「子どものためにとやれば際限がない、先生がゆとりを持って勤務することが、子どものため になるので早く帰るように」と校長から話しがある
例:職員室の扉に「8時には仕事を終えよう」の貼り紙を掲げる
例:週案の反省欄の記述は書かなくてもよしとする
4.教職員の定数増 と少人数学級の拡大
長時間過密労働の背景には、仕事量に見合う定数が配置されていないもとで、時間外勤務を余儀なくされている実態があります。先生の数を増やすとともに、研修や調査・報告書の提出などを厳選し、忙しさを解消して子どもともっと向き合える時間を確保し、教職員が生き生きと働き続けられる学校づくりが求められます。また、来年度よりようやく国が学級の定数を見直し、当面1年生から35人学級を実施することを決めました。愛知県の独自措置を3年生に拡大させるとともに、豊田や安城のように岡崎市でも独自措置を講じるよう関係機関への働きかけを求めるものです。